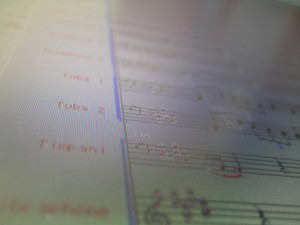
家庭教師の夏期講習も終わり、だいぶ時間に余裕が出てきました。そんなわけなので、今日はめずらしく日付が変わる前にブログを書こうかと思います。
今日もほぼ一日中、編曲作業をしていました。編曲という言葉にはじつは 2 種類の意味があります。ひとつは元の曲と違う楽器で演奏できるよう書き換える編曲、もうひとつは元の曲と違う構成や印象になるように作り変える編曲です。
今作業している編曲は、異なる曲を途切れめなく演奏できるようにつなげつつ、元の曲と違う楽器で演奏できるように編曲する作業です。前述のふたつの編曲作業を両方半分ずつやっているような具合、といったらいいと思います。
今回はさらに、実際の演奏会で演奏するための編曲なので、各楽器の音量のバランスも検討しなければなりません。いや、楽器自体の性能の限界を考慮に入れなければならない、という方が適切かもしれません。
特にオーボエやファゴットなどの木管楽器は、普段テレビなどで聴いている印象と異なり、驚くほど小さな音量しか出ません。そんな木管楽器をトランペットなどの金管楽器と一緒に演奏させると、たちまちバランスが崩壊してかき消されてしまいます。
じゃあトランペットたちになるべく弱い音で演奏させたらいいか、というとそうでもありません。ある程度は吹かないと、トランペット自身の音に魅力がなくなってしまいます。それに、トランペットは音が高くなるほど弱く吹くことが困難になったりもします。
うまくいかないものを、いかに取り繕うか。それこそが編曲者の使命だと思っています。楽譜に書かれていることを直感的に演奏するだけでいい演奏になる、そんな編曲ができれば幸せです。今のところ、まだまだ勉強中ですが。

コメントを残す